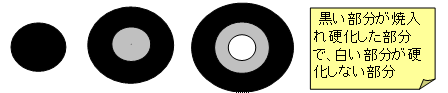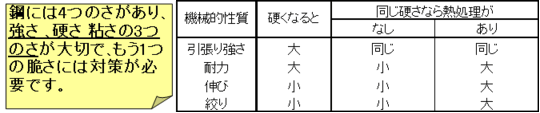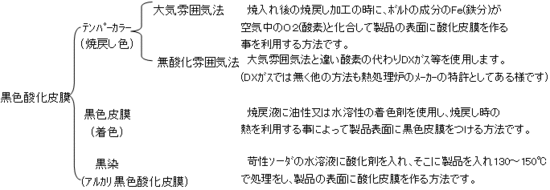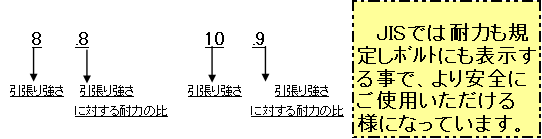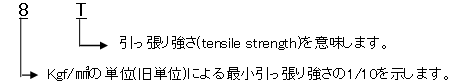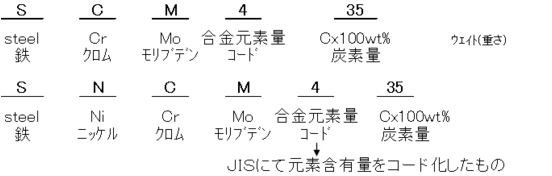皆さんは特殊用途鋼のステンレス鋼材について次の様に記憶されているのでは
ないでしょうか。(ステンレス鋼とは全体の12%以上クロムを含んだ鋼)
SUS304 オーステナイト系
SUS430 フェライト系
SUS410 マルテンサイト系
上記の様にそれぞれ系とついてますよね。オーステナイト等の言葉は鋼の組織を
表しているもので、ステンレス鋼に限定したものではありません。それぞれの組織
名は発見した人名等が付けられています。代表的なものについて記載しておきます。
オーステナイト
FeとCの合金において、温度が723℃以上において
安定的な組織で、常温では存在しない組織であるが、
NiやMnを多く含む事によって安定する組織です。
フェライト
鉄(Fe)に最大0.02%のCが含まれた組織で、ほぼ純鉄
に近く、鉄鋼組織の中で最も軟らかく、延性も大きい。
ラテン語のFerrum(フェルーム)からきています。
マルテンサイト
オーステナイト組織を急冷した時に出来る組織で硬くて脆
い組織です。
トルースタイト
マルテンサイト組織を400℃で焼戻しした時に出来る組織
軟らかく脆さがとれた組織です。
ソルバイト
マルテンサイト組織を600℃で焼戻しした時に出来る組織
粘さが発揮される組織です。